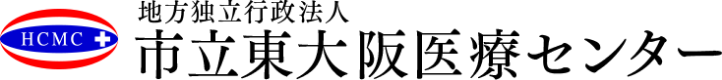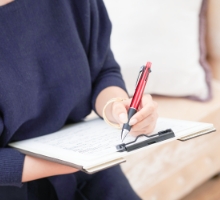スタッフインタビュー
スタッフインタビュー

市立東大阪医療センターの肺がん診療
東山 聖彦 / 特任院長(呼吸器外科)
市立東大阪医療センターの肺がん診療の概要
市立東大阪医療センターは520床、36診療科を有する「地域がん診療連携拠点病院」です。私の担当診療科である呼吸器外科では、肺がん、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、自然気胸、外傷性血気胸、膿胸など多岐にわたる呼吸器・縦隔疾患の外科治療を3名のスタッフで行っています。その中で主たる疾患の肺がんについては、呼吸器内科常勤医が欠員のため、肺がんの診断や内科的治療(薬物療法、放射線治療、緩和ケア)の患者さんも診療しています。
外科治療については、内視鏡の機械や器具の発達により、胸腔鏡下または胸腔鏡補助下の低侵襲手術を行い、肺がんでは1週間ぐらいの入院期間となっています。最近では80歳を超える高齢者の手術も増加し、全体の40%近く占めるようになっているため、理学療法士や栄養士などに積極的に術後回復に介入していただき、早期退院となるように努めています。
一方、外科治療の対象とならない肺がん患者さんについては、肺がん診療ガイドラインに順じて内科的治療を行っています。薬物療法については、治療に先立って気管支鏡検査などから得られる生検標本を用いて遺伝子検査を行い、その結果に基づいて従来の抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤などの薬剤(レジメン)選択を行いますが、必ず院内薬剤師と大学の腫瘍内科医らを含むWEBカンファレンスで最終決定をしています。放射線治療については、従来からSBRT(定位放射線治療)やIMRT(強度変調放射線治療)を行ってきましたが、2025年春より最新鋭の治療装置が導入されるので、その治療効果が期待されています。
表1に、市立東大阪医療センターの最近の呼吸器外科治療と肺がん診療実績を示しました。
表1:市立東大阪医療センターの呼吸器外科治療と肺がん診療実績 (2020~2024年)
| 年 | 外科治療 | 肺がん薬物療法(1次治療) | 肺がん放射線治療(SBRT) | 肺がん緩和ケア(1次治療) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺がん | 転移性肺腫瘍 | 縦隔腫瘍 | その他 | 合計 | 複合免疫療法 | 複合免疫療法+放射線 | 免疫療法 | プラチナを含む抗がん剤 | 分子標的薬 | その他 | 合計 | |||
| 2020 | 41 | 5 | 9 | 17 | 72 | 24 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 46 | 15 | 14 |
| 2021 | 64 | 17 | 6 | 32 | 119 | 32 | 6 | 5 | 4 | 13 | 3 | 63 | 4 | 9 |
| 2022 | 40 | 15 | 5 | 30 | 90 | 29 | 6 | 5 | 5 | 12 | 0 | 57 | 5 | 20 |
| 2023 | 60 | 10 | 2 | 26 | 98 | 17 | 5 | 11 | 16 | 11 | 10 | 60 | 12 | 17 |
| 2024 | 53 | 7 | 3 | 34 | 97 | 15 | 0 | 3 | 11 | 16 | 1 | 46 | 2 | 27 |
肺がん治療の最近のトピックス
市立東大阪医療センターの新たな取り組み
肺がんの治療に関して、最近のトピックスを2つ述べたいと思います。
先ずは、局所進行肺がんに対する手術を組み合わせた集学的治療(特に手術の前後に行われることから周術期治療といわれます)の飛躍的進歩の話題です。局所進行とは肺がんが胸腔内に留まっているものの縦隔リンパ節などに広がっているケースで(通常は病期III期が対象)、完全切除ができないことも多く手術のみの治療成績は全く満足できるものでありませんでした。もちろん手術とその前後に薬物療法(抗がん剤治療)や放射線治療を組み合わせた周術期治療は今迄にも試みられてきたのですが、近年、薬物療法に免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬を加えることで、一気に治療成績が改善されることが明らかになってきました。現在、これらの薬剤の種類や組み合わせ方法、手術前や手術後のどのタイミングの投与なのかなど研究され、次々と新しい知見が得られており、期待は大きいです。
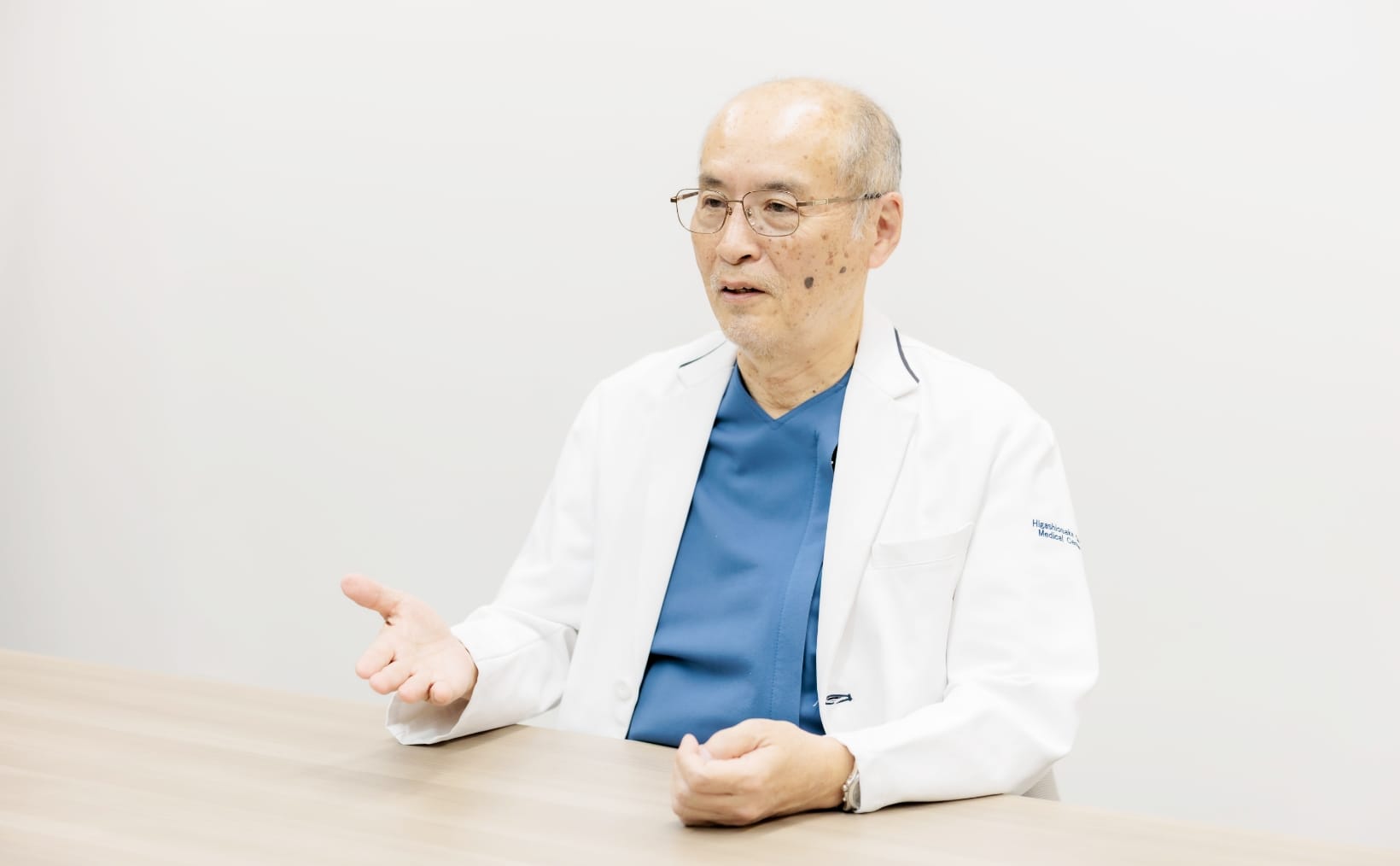
ただし手術を挟む治療期間が長く、それなりの副作用やリスクもあるため、少なくとも治療前より良好な全身状態(PS)と日常生活動作(ADL)が必要です。市立東大阪医療センターもこのような手術を含む新しい周術期治療の適応あるケースには、すでに積極的に治療導入しています。
他方は、高齢者肺がん患者さんの増加による医療現場の課題です。私が肺がん外科治療を始めた1990年頃では、治療対象患者さんの全国平均が64歳でしたが、昨今は全国平均が71歳となり、高齢者の多い当地域では74歳となっています。
さらに市立東大阪医療センターの80歳以上の外科治療例はすでに40%近くを占め(上述)、薬物療法も対象患者さんの37%に対し積極的な治療されており、90歳以上の薬物治療も稀ではなくなりました。治療対象の選択には、もちろん年齢値のみでなく、心肺機能、重篤な併存症、日常生活の状態、患者さんの理解度などが評価項目となります。外科治療では、上述の胸腔鏡下で行うことで創部を小さくしたり、肺切除量を減らした縮小手術を行います(通常は肺葉切除が標準的な切除量)。麻酔や手術が困難な早期の肺がんでは、放射線治療(SBRT)を選択します。薬物療法では、薬剤副作用の少ない薬剤や量的調整を行います。このような工夫は必要ですが、さらに患者さんの社会・生活環境の評価も重要です。
昨今の高齢者は独居や家族がいない(身寄りのない)場合が実に多く、本人のみでは意思決定ができず、副作用を見逃したり、重篤になってからの病院受診となるため治療継続が困難になりがちで、治療成績も悪くなるのが現状です(我々は2024年に英文論文雑誌「Cureus」に報告しました)。そこで院内多職種からなる支援チームや、地域の様々な社会的リソースや支援施設との連携を、治療前から介入し強化しています。市立東大阪医療センターでは看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、がん相談員、地域医療連携室スタッフらによる院内支援チームや、かかりつけ医(在宅医)や訪問看護ステーション、介護施設などと密な連携を行いながらがん治療を進める体制を構築しています。とは言え個々の高齢者肺がん患者さんの社会・生活環境は一様でなくその求めるニーズも様々のため、満足できる支援を提供するにはまだまだ不十分で、今後の課題と考えています。
我々からのメッセージ
大阪府中河内医療圏の肺がん医療のトップランナーを目指して
市立東大阪医療センターがある大阪府中河内医療圏には大学病院がないので、市立東大阪医療センターはがん診療の中核拠点病院として高度な専門的医療の提供が求められます。特に肺がん診療は、次々と新たな手術器具、薬剤、放射線治療装置が開発導入され、その治療は低侵襲でしかも高い治療効果を得ることを目標に日進月歩で進化しています。市立東大阪医療センターもこれら最新の肺がん医療を提供できるように、常にその治療体制の更新をしています。加えて肺がん患者さんにとって満足していただけるような治療となるには、院内および地域の多職種からなるチームワーク医療と様々な支援が必要です。「肺がん医療のトップランナー」を目指し、これらの連携体制も十分となるよう弛まぬ努力を推進していますので、安心して市立東大阪医療センターを受診していただければと思います。