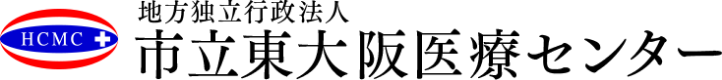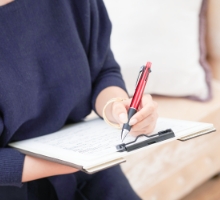スタッフインタビュー
スタッフインタビュー

母と子の未来を守る、確かな医療
前中 隆秀 / 主任医長(産婦人科)
はじめに
私の専門分野である周産期医療は、妊娠および分娩に関わる母体・胎児の管理と出生後の新生児の管理を主に対象とする医療です。すなわち、これからお母さんとなる妊婦の方々や生まれてくる赤ちゃん達の安全を守ることで、地域の未来を守る医療とも言えます。
私はこれまで、大学病院や地域の基幹病院など、リスクの高い妊産婦の方々に対応可能な都道府県が定める周産期母子医療センターで勤務し、妊娠中や分娩前後に命に関わる状況に陥ったお母さん達の治療に携わってまいりました。
これまでの経験を通して、ここでは、産科医の立場から、主に母体に対する妊娠・分娩に関する市立東大阪医療センターの取組みについて紹介します。
お産のリスクについて
「出産」という言葉について、皆さんはどの様なイメージをお持ちでしょうか。「新しい命の誕生」などのプラスのイメージと同時に、「痛み」や「危険」などのマイナスのイメージも頭に浮かぶのではないでしょうか。
実際、分娩は、医療の介入がなければ、約1/150-200の確率で死亡を含む重篤な状況に陥るとされています。これは、交通事故により、死亡を含む重症以上となる確率と比較し、約20倍高い数字です。一方、最終的に母体死亡に至る確率は約1/20000-25000の確率であることから、分娩における危険な事象の99%を医療が未然に防いでいると言えます。
つまり、お母さんが安全に出産を終え、赤ちゃんと共に無事に家族のもとへ帰っていただくためには、適切な医療資源が整った施設において妊婦健診や分娩をおこなうことが、非常に重要なポイントのひとつであると言えます。
産科救急における周産期医療と救急医療の連携
産後の大量出血等、妊娠中から分娩後における妊産婦の方々の命に関わる疾患、いわゆる産科救急疾患に要する治療戦略は、比較的健康な人が外傷による出血等により急激に全身状態が悪化することから、交通事故等に伴う外傷救急疾患との類似点が多く、外傷救急疾患の治療に習熟した救急医との連携が非常に大切であると考えられており、国においても、平成20年以降、周産期医療と救急医療の連携を推進しています。

市立東大阪医療センターの産科救急への取り組み
市立東大阪医療センターは、約80万人の人口を抱える、東大阪市、八尾市、柏原市からなる中河内地域において、高度急性期・急性期医療を提供する地域中核病院の役割を担うほか、大阪府が認定する「地域周産期母子医療センター」でもあり、地域におけるハイリスクな妊娠・分娩および新生児に対応する役割も担っています。また、隣接する大阪府立中河内救命救急センターは、命に関わる外傷等の救急医療における地域の中核としての役割を担っています。
しかし、これまで、産後の大量出血等の産科救急疾患については、中河内地域で対応することが必ずしも容易ではなかったことから、大阪市内の医療機関へと搬送する症例が少なくありませんでした。
そこで、中河内地域の妊婦の方々に、より安心して妊娠期間を過ごし、安全に分娩に臨んでいただくことを目的として、市立東大阪医療センターと大阪府立中河内救命救急センター(以下、両センター)は、産科救急疾患に対応する連携体制を整備し、令和7年4月より本格的に当該疾患の受入れを開始しました。
これにより、命の危険が迫っている妊産婦の方々に対し、大阪市内の医療機関へと搬送する場合と比べ、より早いタイミングで救命のための治療を開始することができることから、中河内地域における、産科救急疾患への対応能力を向上させ、地域の妊産婦の方々の安全や安心に貢献するものであると考えています。
地域の妊産婦およびご家族の皆さんへ
市立東大阪医療センターは、センター内の産婦人科、小児科、麻酔科、手術部等の産科救急医療関連部署および大阪府立中河内救命救急センターと適切に連携し、これからお母さんとなる方々に、妊婦健診・分娩について、より安心して臨んでいただけるよう、引き続き、安全な体制づくりに努めてまいります。また、産後ケアやメンタルサポートにも力を入れており、産後うつ等の予防や改善を含め、より良い形で赤ちゃんとの生活をスタートできるよう、支援させていただきたいと考えています。
地域の皆さんには、妊娠や分娩のもつリスクを適切にご認識いただくとともに、妊婦健診や分娩への市立東大阪医療センターの取組みや両センターの産科救急に関する連携についてご理解いただき、安心して市立東大阪医療センターをご利用いただきたいと考えています。